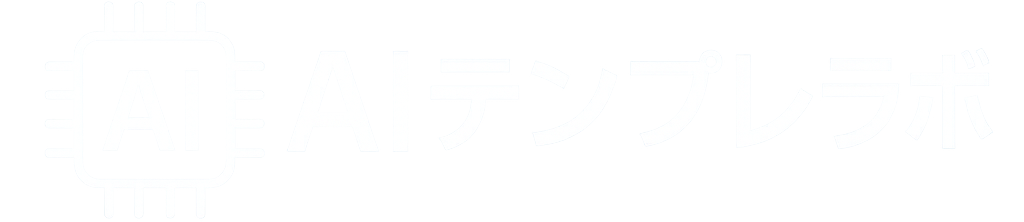「生成AIパスポート」という資格が登場し、SNSやニュースで目にする人も増えてきました。
しかし “そもそも何なのか”、“取るとどんな意味があるのか”、“試験は難しいのか” と疑問を抱く方も多いはず。
実際に取得したリアルな体験を交えて解説します。
生成AIパスポートとは?
試験の概要と目的
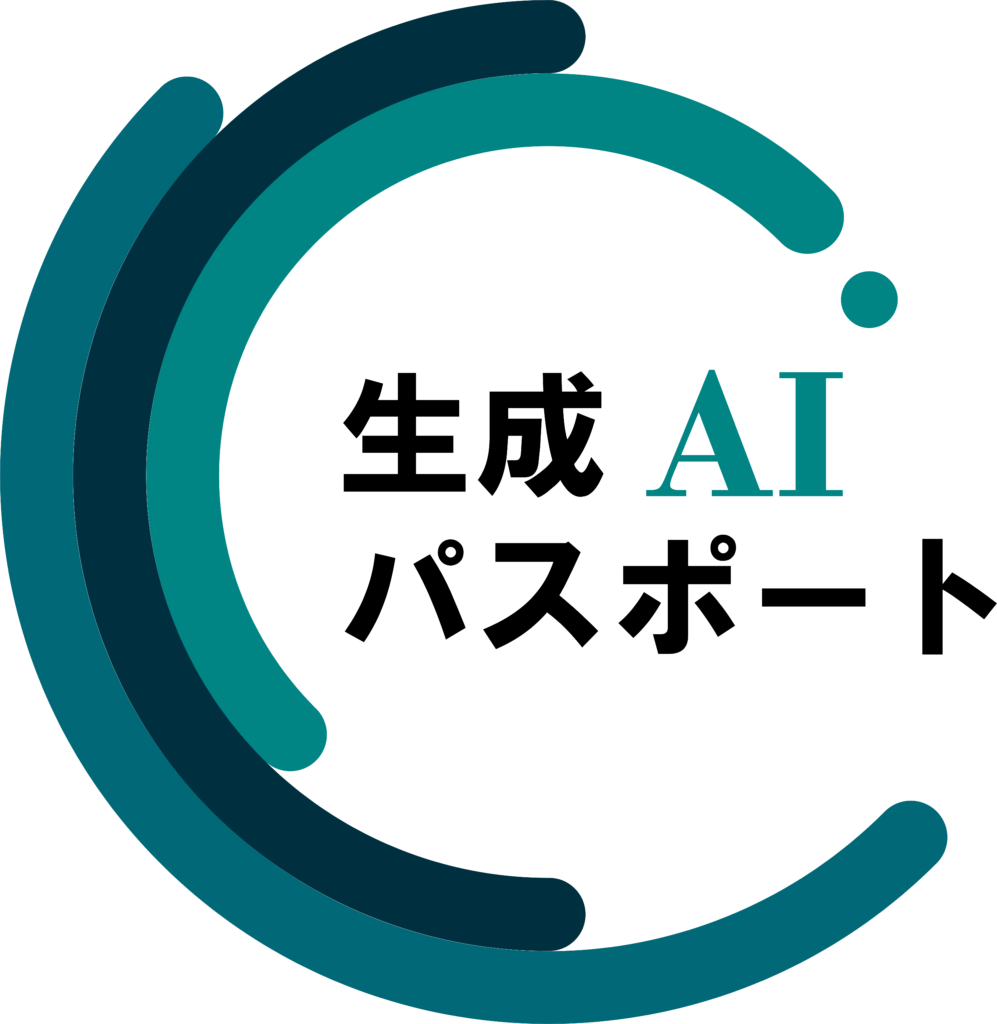
(出典:GUGA「生成AIパスポート 公式概要」)
生成AIパスポートは、一般社団法人 生成AI活用普及協会(GUGA)が提供する認定資格で、AIを「つくる側」ではなく「使う側」に必要なAIリテラシーを証明するものです。
試験はオンラインで実施され、生成AIの基本的な仕組みや社会的影響、リスクやガイドラインなど、幅広い領域から出題されます。
特徴的なのは「専門家向け」ではなく、ビジネスパーソンや学生など幅広い層が対象である点。つまり、AIエンジニアになるための深い数学的知識は不要で、AI活用の基礎を理解できているかを問う設計になっています。
私自身も受験しましたが、「AIを仕事や学びにどう取り入れるか」を考える良いきっかけとなる試験でした。
「AIリテラシー」とは

生成AIパスポートで重要なのは「AIリテラシー」という考え方です。
リテラシーとは、単に知識を暗記することではなく、正しく理解し適切に使いこなす力を指します。
具体的には、AIがどのようなデータで学習しているのか、偏りや著作権の問題をどう考えるか、そして生成AIを業務に導入する際にどんなリスク管理が必要か──といった観点です。
試験問題も「AIができること・できないことを理解しているか」を問う内容が中心で、現場で役立つ考え方を学べる仕組みになっています。
私は外資系コンサルの現場で「AI導入プロジェクト」に携わっていますが、クライアントから必ず聞かれるのは「リスク」と「適用範囲」。まさに試験で問われるリテラシーが実務に直結していると感じました。
実際に受けてみて感じたこと
私自身が生成AIパスポートを受験した際の率直な印象は、「知識確認の試験」であると同時に「安心感を得られる資格」だということです。
試験内容は基礎的な選択問題が多く、学習していれば難しくありません。
ただ、生成AIに関するニュースやSNSの断片的な情報しか知らない人にとっては、体系的に整理する機会になると思います。
実際に合格通知と証明書を受け取ったとき、外部に対して「自分はAIを理解している」と伝えやすくなりました。
資格そのものよりも、「学び直し」と「第三者からの信頼性」が大きな価値だと感じます。特に転職や副業を考える人にとっては、肩書きのひとつとして活かせる資格です。
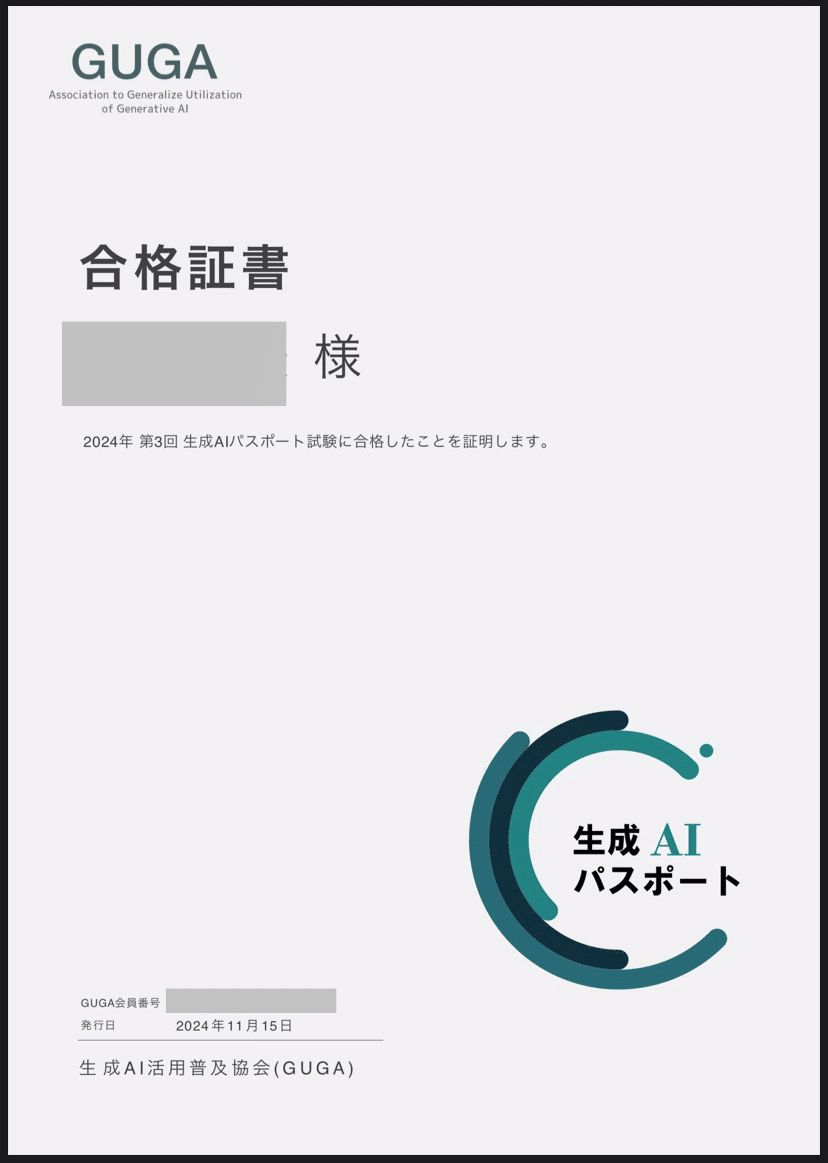
(実際の合格証)
生成AIパスポートを取得するメリット
就職・転職・副業でのアピール材料になる

AIに関連する資格は増えてきましたが、生成AIパスポートは「幅広い層に対応している」ことから、履歴書や職務経歴書に書きやすいのが特徴です。
採用担当者やクライアントに「AIを理解している人材」としてアピールできるため、IT業界だけでなく営業・マーケティング・教育など幅広い業界で活かせます。
私が副業相談を受ける際も「資格で差別化できるのか?」という質問がよく出ますが、生成AIパスポートは知名度も高まりつつあるため、一定の信頼性を示すには効果的だと考えます。
特に未経験でAI関連のキャリアに挑戦したい人にとっては、最初のステップとして非常に有用です。
生成AIを活用するスキルの証明になる
生成AIパスポートは「実技試験」ではありませんが、活用スキルを裏付ける基礎知識を持っている証明になります。
例えば、ChatGPTや画像生成AIを業務で導入する際、ただ使うだけでなく「どういう仕組みで生成されているのか」「リスクをどう避けるのか」を理解していることが重要です。
私がコンサル現場で感じるのは、AIを触っている人は多いものの、仕組みや限界を知らないまま使う人が意外と多いということ。
その点、生成AIパスポートは「正しく使うための基礎知識」を体系的に学べるため、実務に直結する強みとなります。
資格取得後は、ただの利用者ではなく「安心して任せられる人材」として評価されやすくなる傾向があります。
企業が求める「AI人材像」に近づける
近年、企業がAI導入を進める際に重視しているのは「専門家」だけではなく、「AIを理解して使いこなせる一般社員」です。
生成AIパスポートは、まさにそのニーズに応える資格です。
「AI人材の充足状況についての調査によると、“足りていない”と回答した企業は 59.6% にのぼっています。」
引用元:『人事白書2024』(日本の人事部)「AI人材は“足りていない”が約6割」 日本の人事部
このように、AI人材が不足していると認識している企業は半数以上に及び、資格保有者やAIリテラシーを持つ人材には明確な需要があるといえます。
企業はAIに詳しい一部の技術者だけでなく、営業・人事・企画といった部門でもAIを使える人材を必要としています。
私が日々向き合う上場企業のクライアントの方々からも、「AIリテラシーを全社員に持たせたい」という要望をよく耳にします。
生成AIパスポートを持っていることは、その潮流にフィットしている証明になり、評価ポイントとなり得ます。
特に「DX推進」「AI活用プロジェクト」のメンバー候補として名前が挙がるきっかけにもなるそうです。
生成AIパスポート試験の難易度は?
出題範囲と勉強方法のポイント
生成AIパスポートの出題範囲は、生成AIの基礎、AIの仕組みと種類、著作権や倫理、セキュリティなど多岐にわたります。
ただし数学やプログラミングは不要で、公式テキストや模擬問題を活用すれば十分対応できます。
私の学習方法はシンプルで、公式が提供する学習資料を一通り読み、模擬問題を繰り返し解きました。
ポイントは「用語を正確に理解すること」と「最新のAIニュースに目を通しておくこと」。
出題傾向としても、最新の生成AI事例に絡めた問題が多かった印象です。
勉強時間は20〜30時間程度あれば合格圏内に入れるはずです。
合格率と実際の難易度
公式発表によると、生成AIパスポート試験の合格率は比較的高く、6〜7割程度の受験者が合格していると言われています。
「2024年10月に実施された生成AIパスポート試験では、3,733名が受験し、そのうち2,828名が合格、合格率は75.76% でした。」
引用元:GUGA「生成AIリスクを予防する資格試験 2024年 第3回 生成AIパスポート試験(結果発表)」 生成AI活用普及協会(GUGA)
「2025年2月実施の試験では、6,590名が受験し、5,104名が合格、合格率は77.45% との発表があります。」
引用元:GUGA「2025年2月 生成AIパスポート試験 結果発表」 生成AI活用普及協会(GUGA)
つまり「しっかり勉強すれば誰でも合格可能」というレベル感です。
試験問題は4択の選択式で、難解な計算問題は出ません。
ですが、用語や概念を曖昧に覚えていると不正解になりやすいため、基礎を押さえておくことが大切です。
私の受験体感では、ITやAIに触れたことがある人なら比較的スムーズに進められるでしょう。
一方、AI未経験者でも学習時間をしっかり確保すれば十分に合格可能です。
「難しい資格」というより「準備すれば取れる実用資格」と言えます。
実際の学習体験と感想
私自身はAIコンサルタントという立場で受験しましたが、普段の業務で使っている知識に加え、公式テキストで整理したことで安心して臨めました。
印象的だったのは「合格後の自信の持ち方」が変わること。
資格があることで、クライアントや同僚に対して「AIリテラシーがある人材」として認識されやすくなり、実際にプロジェクトの声がかかることも増えました。
これから受験を考えている方に伝えたいのは、「完璧を目指さなくても良い」ということ。
試験は広く浅く問われるため、まずは全体像を押さえて、模擬試験で7割正解できる状態を目標にするのがおすすめです。
学習を通じて得られる知識は必ず実務やキャリアに役立ちます!
まとめ
生成AIパスポートは、ただの資格ではなく“学び直し”のきっかけになる存在です。
私自身も、資格取得を通じて改めてAIを俯瞰できた実感があります。
キャリアの武器にするのはもちろん、“安心してAIを使える力”を身につけるチャンスだと思います。
ぜひ挑戦してみてください!
要点整理
生成AIパスポートはAIを使う人向けの基礎資格
学習そのものが実務に直結するAIリテラシーを育てる
就職・転職・副業でのアピールに有効
難易度は高くなく、準備すれば誰でも合格可能